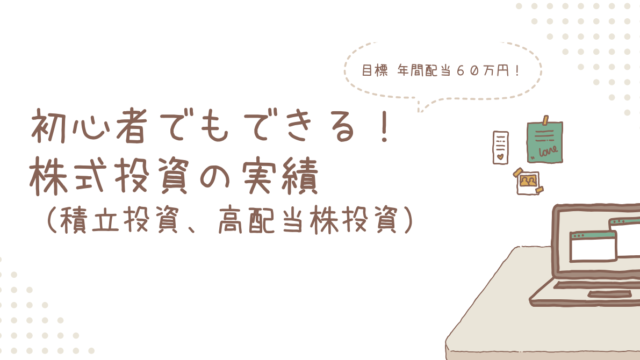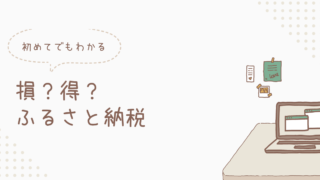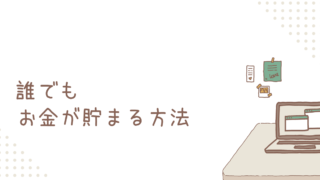初めてのふるさと納税 経験者が手順と失敗しない方法を簡単に解説
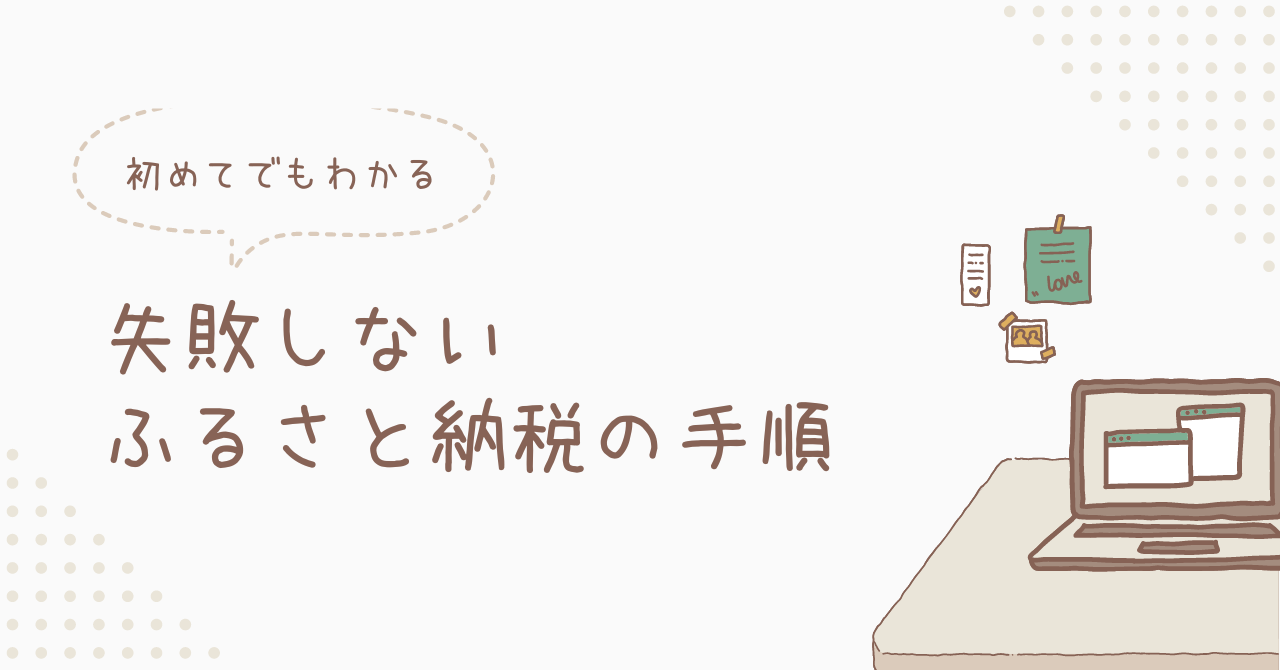
皆様、本日は「おんおふはうす」をご訪問いただきありがとうございます!
今回、お話するのは「ふるさと納税」についてです。
「ふるさと納税をやりたいけど難しそう・・・」、
「始めてみたいけど、なにからすれば良いのかな?」
そう思って、ふるさと納税を始められない方、意外と多いのではないでしょうか?
この記事では、私自身の経験や失敗談も踏まえて、初めての方でも簡単に始められるように、ふるさと納税について解説したいと思います。
よくある失敗例なども紹介しますので、参考にしつつ、スムーズにふるさと納税を始めて、日々の生活を少しでも楽しく豊かなものにして行きましょう♪
初めての方にわかりやすい解説を心掛けていますので、身近な方から「ふるさと納税」について聞かれた際にも、是非、このページを紹介してくださいね!
そもそも「ふるさと納税」とはどのような制度かというと、
ふるさと納税制度の概要
ふるさと納税とは、自分が選んだ応援したい自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、自治体から返礼品が貰え、さらに控除を受けられる限度額から2,000円を差し引いた部分について、翌年の所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)
控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体が5か所以下である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できます。
※自治体とは都道府県や市区町村のことを言います。
↑難しくてよく分からないという方のために、物凄く簡単に説明すると、
自分が選んだ自治体に対し、上限範囲内の金額で寄附をすると来年度支払う予定の税金を前払いしたという形になり、さらに返礼品が貰える制度です。
ただし、この制度を利用するためには、手数料2,000円と翌年に確定申告をする必要があります。
今、なんだか面倒くさそうだな〜と思った方も安心してください!
手数料の2,000円は寄附した金額から差し引きされるため、皆さんが別に支払い手続きをする必要はありません。
また、寄附先が5か所以下なら、確定申告をしなくても、郵送されてきた書類に記入し、免許証等の本人確認書類のコピーを貼り付けて返送するだけで、簡単にふるさと納税制度の適用を受けることもできます。
ふるさと納税の概要は何となくお分かりいただけましたか?
本当にお得なのかどうか分からないな~という方は、先にこちらの記事【ふるさと納税って本当にお得なの?損をしてしまう場合】をご覧ください。
ここからは効率的にふるさと納税を行う手順をご説明します。
ふるさと納税の手順
- 自分の控除限度額を調べる
- ふるさと納税申請サイトを決める
- どの自治体に寄附するかを決める
- 確定申告かワンストップ特例制度どちらを利用するか決める
- 寄附申請を行う
- 確定申告、ワンストップ特例制度を行う
- 所得税・住民税から控除される(※ワンストップ特例制度は住民税のみ)
自分の控除限度額を調べる
まずは、自分がどれだけふるさと納税できるか限度額の目安を調べます。
ふるさと納税をする際に限度額以上の寄附をしてしまうと、ただの実費負担となり、割高な買い物をしてしまうことになるので必ず確認しましょう。
調べる方法ですが、基本的にふるさと納税申請サイトで調べることができます。
おおよその金額が分かればいいという方は「楽天市場ふるさと納税かんたんシミュレーター」がおすすめです。
自分の情報を細かく入力する必要がありますが、限度額のぎりぎりまで寄附をしたいという方は「楽天市場ふるさと納税詳細版シミュレーター」がおすすめです。
表示されている「寄附上限額(目安)」から2,000円を引いた金額が所得税や住民税から控除される金額です。
とはいえ、計算時はあくまでも目安であることを理解しておきましょう。
次のような場合は控除限度額が減少します。
・景気等の影響を受け収入が減った。
・医療費控除、住宅ローン控除等を申請する。
他にも、転職や退職などで収入が少なくなる方や、自営業の方で赤字になる年がある場合は要注意です。上限額を超えてしまうと自己負担が増えるだけでなく、損をしてしまう場合もあることは覚えておきましょう。
私は、前年の情報で計算をして、控除限度額より少しだけ少ない金額を寄附しました。
どのサイトで納税するかを決める
自分の限度額が分かったら、次はどのサイトを利用するかを決めます。
現在、ふるさと納税サイトは数多く存在しており、どのような基準で決めたらいいか分からない方も多いと思いますが、それぞれのサイトには特徴があります。
返礼品の種類が多い、登録している自治体の数が多い、他のサイトにはない返礼品がある、Amazonや楽天のポイントがつく等々・・・
皆さん自身がどういったことを重視するかでサイトを選んでみましょう。
ちなみに、私がサイトを選ぶ時に重要視をしたことは
・Amazonのポイントが多く貰える。
・自分が寄附したい自治体(返礼品)がある。
といった点で、実際に初めて利用したサイトは「ふるさと本舗」で、2年目以降は「楽天ふるさと納税サイト」を利用しています。
そのほかにも寄附先を調べやすかったり、自治体や返礼品をお気に入り登録できるといったサイト自体の使いやすさを重視していいかもしれませんね。
利用するサイトが決まったら登録をしましょう。
ふるさと納税サイトは一度登録したら必ずそこを利用しなければいけないわけではありません。
固く考えず、まずは利用してみて、不便を感じた場合は違うサイトを利用してみましょう。(私自身も利用するサイトを変えてみたので!)
ただし、複数のサイトを利用した場合、寄附金額を合算して管理する必要があります。
うっかり他のサイトで寄附したことを忘れてしまい、限度額以上に寄附してしまった!なんてことがないように気をつけましょう。
どの自治体に寄附するかを選ぶ
ふるさと納税制度の本質は、自分が応援したい自治体を選んで寄附をすることだけど、やっぱり自治体からの返礼品に魅力を感じている人も多いよね!
自分のふるさと(出身地)やお目当ての返礼品、応援したい自治体など、様々な選択肢から自分が寄附する自治体と返礼品を選びます。
また、ふるさと納税の支払い方法は、クレジットカード払い、電子マネー、コンビニ払い、郵便振替、銀行振込、現金書留、納付書払い、自治体への直接持参などがあります。
ただし、寄附先の自治体によっては対応していない支払い方法もあるので、寄附先を選ぶ時には注意しましょう。
寄附申請の時に、復興支援、商業施設整備、環境保護、教育の充実など、自分が寄付したお金を何に使ってほしいか希望することも出来るから、直接的に寄附先の自治体やそこに住む方たちを応援している気持ちになるよね!
ここで気をつけてほしいことは、自分が今住んでいる(住民票がある)自治体には寄附をしないこと!
自分が住んでいる自治体に寄附をしてもふるさと納税制度の対象とはならず、返礼品はもらえないのでご注意ください。
プチ情報
2008年5月から運用が開始されたふるさと納税制度ですが、利用者が増えることに伴い、自治体間の競争が加熱し、寄附者を多く募るために返礼品に加えてAmazonギフト券を配布したり、地元の特産品とは呼べないような物を返礼品にする自治体や寄附額の8割を返礼品に当てるような自治体が現れました。
総務省は、このような状態では、地域の特産品を返礼品にしている自治体が報われず、ふるさと納税制度の本来の目的とは異なる結果となってしまうと、2019年4月に返礼品のあり方について各自治体へ通知しました。
しかし、状況が改善されなかったため、総務省は2019年6月にふるさと納税制度の一部改正をおこない、寄附金額に対する返礼品の金額の割合を上限3割とするルールを設けました。さらに、ルールを守らない自治体はふるさと納税制度の適用から除外されることになり、実際に除外された自治体も存在します。
今もふるさと納税サイトには還元率110%の返礼品があるけど大丈夫なの?
さすが!良いところに気付いたね!
ふるさと納税サイトでの還元率50%や110%といった表示について説明します。
あれ?さっき返礼品の上限は3割以下に設定されていると言っていたのに、どちらが正しいの?と疑問に思われた方は、さすがです!
→答えは「どちらも正しい」です。
なぜなら「返礼割合」と「還元率」という言葉に使用する数値が違うからです。
では、実際にそれぞれ数値について見ていきましょう。
返礼割合の計算は、寄附金額÷返礼品の調達額
・寄附金額
・返礼品の調達に要した金額
(自治体が何円払ってその返礼品を仕入れたか)
還元率の計算は、寄附金額÷返礼品の市場価格
・寄附金額
・返礼品の市場価格
(一般的に返礼品が何円で売られているか)
このように計算の基準となる金額が異なるため、30%以上(3割以上)の数字が表示されていても問題がないということになります。
単純に金銭的な価値だけを考えれば還元率が高いほど、寄附した金額に近い価値の返礼品が貰えるのでお得ということになりますね。
ふるさと納税サイトのお気に入り登録の機能なども活用して、納得行くまで、じっくりと迷ってみるのも楽しい時間ですよ。
ただし、人気が集中して、すぐに無くなってしまうような返礼品もあるので、気をつけてくださいね。
確定申告をするか、ワンストップ特例制度を利用するかを決める
会社員で確定申告が不要という方は、ワンストップ特例制度を利用できます。
ただし、ワンストップ特例制度を利用するには以下の条件を満たす必要があります。
・確定申告や住民税申告を行わないこと(医療費控除など)
・ふるさと納税先の自治体が1年間(1月1日から12月31日)で5自治体以下であること
寄附申請をする
ここまでのステップが終わったら、実際に寄附申請をおこないます。
寄附申請をすると基本的にはキャンセルできないので注意してください。
まず、ふるさと納税サイトのカートにいき、購入手続き・決済画面に移行し、
申請者の住所や寄附金の用途などの必要情報を入力します。
この際、ワンストップ特例制度を利用するかどうかも選択し、
最後に支払い方法を選択して寄附申請は終了です。(事前準備をしておけばアッという間に終わりますよ!)
支払いが完了したら、あとは自治体から寄附金受領証明書と返礼品が届くのを楽しみに待つだけです!
※ワンストップ制度を利用する場合の注意点
寄附は1月1日から12月31日まで行えるのですが、ワンストップ特例制度を利用する場合、寄附の翌年の1月10日(必着)までに申請書と必要書類を提出しないといけません。
12月末に寄附をした場合、寄附した自治体から申請書が届いてから提出締切までの期間がとても短く、申請期間に間に合わない場合があります。
ワンストップ特例制度を利用する方は少し余裕をもって寄附するようにしましょう。
ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄附の翌年1月1日までに名前や住所の変更があった場合は、申請書を提出した自治体に、寄附の翌年1月10日までに申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
私が困ったこと
ふるさと納税サイトで購入手続きをしていると、「取引判定保留(友人判定)です。[G30]」とエラーが表示され決済が完了できませんでした。
このエラーは、カード会社が何らかの理由より、本人の利用であるか確認が必要と判断し、カード決済が利用できない状態になった場合に表示されます。
カードを利用するためには、カード裏面にあるカード会社に連絡をしてセキュリティを解除してもらう必要があります。
カード会社に連絡をすると、カード番号や氏名、購入しようとしていた商品について質問され、回答するとセキュリティを解除してもらえます。
私の場合は、セキュリティを解除してもらったが、決済ができませんでした。
カード会社に問い合わせすると、寄附先の自治体がデビットカード決済に対応するように設定されていない可能性があるとのことでした。
今回、エラーが表示された理由として考えられるのは、ふるさと納税という普段とは異なる利用をしたこと、寄附先の自治体がデビットカードに対応するように設定しておらず、注文が承認されなかったことなどが考えられます。
デビットカードで決済できるかをカード会社側で確認してもらった結果、一つの自治体はデビットカードでの支払いが可能となり、もう一つの自治体はデビットカードでの支払いはできませんでした。
デビットカードで支払いをしたいなど、希望の支払い方法に対応している自治体を寄附先に選ぶようにしましょう。
確定申告、ワンストップ特例制度を行う
自分の控除限度額内でふるさと納税を行った場合、確定申告でもワンストップ特例制度でも、基本的には控除の金額はほぼ同額になるので、どちらを利用しても問題ありません。
確定申告の場合
確定申告の時期は、寄附の翌年2月中旬〜3月中旬頃になるので必要書類を大事に保管しておきましょう。
下記の必要書類を集めた上で、確定申告書に必要事項を記入し提出します。
・寄附金受領証明書または寄附金控除に関する証明書(寄附した自治体から届きます。紛失した場合は再発行も可能なので自治体に問い合わせてみてください。)
・源泉徴収票(会社員の場合は会社から配布されます。)
・簡易帳簿(個人事業主の場合)※青色申告の場合は総勘定元帳など
・確定申告書(会社員はA様式、個人事業主はB様式)※税務署のホームページからダウンロードできます。
ワンストップ特例制度の場合
ふるさと納税を申し込んだ自治体からワンストップ特例制度の申請書が届きますので、必要事項を記入し、身分証明書のコピーを提出します。これだけで手続き完了なので、断然こちらが便利ですよね!
ワンストップ特例制度を申請していることを忘れて、他の要件で確定申告しないように気をつけましょう。
確定申告をしてしまったという方も安心してください!
ワンストップ特例制度を利用した後に、間違えて確定申告もしてしまった場合、お住まいの自治体からワンストップ特例制度の適用を受けることが出来ない旨の文書が送られてきます。
他にも、ふるさと納税を申し込んだ自治体が5団体を超えていた場合やワンストップ特例申請書に記載した住所と現在、住んでいる住所が変わったが申請するのを忘れていた場合も同様にお住まいの自治体から文書が送られて来ます。
このような文書が送られてきた場合は、お住まいの税務署に更正請求書を提出し、寄附金控除の確定申告を追加でやれば問題なく控除を受けることができます。
また、ワンストップ特例制度を申請したけど、医療費控除が適用できるため確定申告に変更したいという方は医療費控除の申告と通常通り寄附受領書を利用して寄附金控除の確定申告をするだけで問題ありません。特に変更手続きや申請は必要ありません。
所得税から住民税から控除(※ワンストップ特例制度の場合は住民税のみ)
所得税からの控除は、確定申告の1〜2か月後に指定した口座へ還付金として振り込まれます。
住民税からの控除は、寄附翌年の6月から住民税が軽減されます。
所得税はお金が入金されますし、住民税は納税額が減少するので、イメージとしては
所得税は返金、住民税は前払いと考えればいいと思います。
控除額の計算方法
ふるさと納税(自治体に対する寄附金)のうち2,000円を超える部分については、一定の上限まで、次のとおり、原則として所得税・個人住民税から全額控除される。
①所得税・・・(ふるさと納税額-2,000円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0~45%(※))が軽減)
②個人住民税(基本分)・・・(ふるさと納税額-2,000円)×10%を税額控除
→①、②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の2割を限度)
③個人住民税(特例分)・・・(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~45%(※)))
この計算式から分かるように、上限額を超えて寄附をした場合は自己負担額が2000円に収まらなくなってしまうため、税額を余分に支払っているのと同じこととなってしまうというわけです。
その他失敗例と対策
・大量に貰える日用品を返礼品に選んだが、家の中に置く場所がなく大変だった。
寄附する前に保管する場所を確保しましょう。
・美味しいものを食べようと複数の自治体に寄附をしたら、冷蔵庫と冷凍庫に入りきらなくて困った。
寄附する時期をずらすなど、保管する場所の状況を把握して寄附を行いましょう。
・貰おうと思っていた返礼品が無くなった。
返礼品の中には人気な物もあるため、すぐに無くなるものには事前に把握し早めに寄附するようにしましょう。
まとめ
私の経験をもとに、ふるさと納税のやり方と注意点などについてご紹介しました。
注意点は以下のとおりです。
- ・自分が住んでいる自治体を寄附先に選んでいないか
- ・自分の控除限度額以上に寄附をしてしまっていないか
- ・確定申告するのにワンストップ特例制度を選択していないか
- ・ワンストップ特例申請後、住所や名前が変更した場合申請事項変更届出書の提出を忘れていないか
- ・ワンストップ特例制度の自治体への用紙の提出は1月10日必着に間に合うか
- ・寄附する自治体の返礼品は人気で少なくなる可能性がないか
- ・寄附金受領証明書をなくさないように保管しているか
- ・返礼品の日用品は事前に保管する場所を確保できているか
- ・返礼品の食べ物は冷凍庫にスペースを考えて、同時に頼みすぎていないか
いまや多くの方がやっているふるさと納税
難しそうと思ってやっていない方もいますが、だれでもできてお得なので是非挑戦してみてください。
ふるさと納税を行い、美味しいものや日用品などを受け取り生活を豊かにしていきましょう!