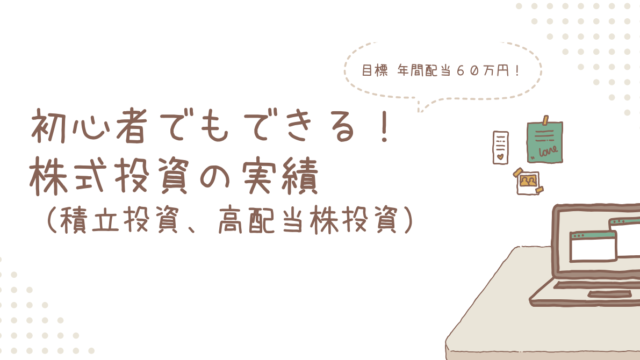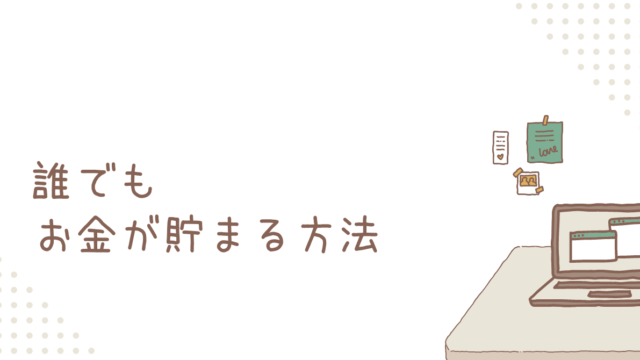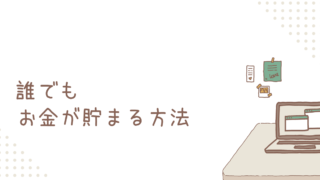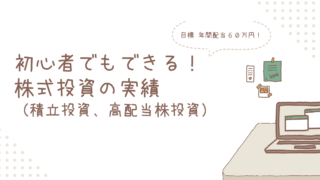投資はした方がいい? 今から始める株式投資 (積立投資、高配当株投資)
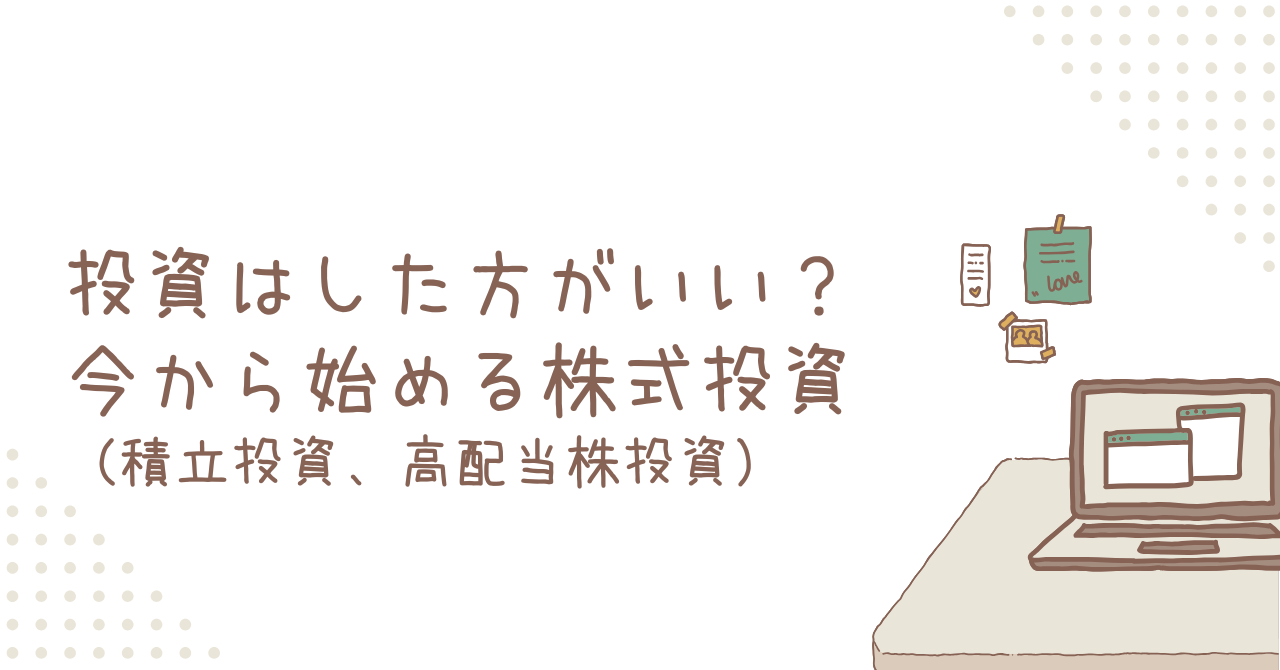
皆様、本日は「おんおふはうす」をご訪問いただきありがとうございます!
今回、お話するのは「株式投資」についてです。
増税、物価上昇により食料品や日用品の値上げがされ、少なからず皆さんの生活にも影響が出ているのではないでしょうか。頑張って貯金をしても銀行預金利息はあってないようなものです。
いかに収入を増やすか、支出を減らすか、資産形成に関心を持つ人が増えてきています。
新NISA制度の開始もあり、今注目されているのが株式投資です。
私は株式投資に関する知識はなく、あまり良いイメージもなかったので、なかなか始められずにいました。
「株式投資をやりたいけど損しそうでこわい」、「騙されそう」「ギャンブルはしたくない」、「始めてみたいけど、なにからすれば良いのか分からない」このように思っている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、株式投資未経験の私が実際に株式投資に挑戦した経験を踏まえてお伝えしていきます。
では、まず基本的なことをおさえておきましょう!
株式会社とは株式を発行し、投資家に販売することで資金を集めて経営を行う会社のことです。また、その会社の株式を保有している人を株主と言います。
株式投資で利益を得る方法は、2種類あります。
購入金額と売却金額の差額益である「キャピタルゲイン」と配当金や株主優待など株式の価格と関係なく得られる利益の「インカムゲイン」です。
多くの人は株式投資と聞くと、キャピタルゲインを想像されるのではないでしょうか。
私も株式の売買を繰り返して利益を出すのが株式投資だと思っていたため、自分には出来ないと思っていました。
株式投資について興味を持ち、勉強していくうちに、自分でも出来そうな方法もありそうと感じました。
保守的な私は、株式投資においてリスクを抑えながら安定した実績を出すために有効的と言われている「長期」「積立」「分散」に基づいた方法で挑戦してみることにしました。
一年間株式投資をやってみた結果(投資実績)
積立投資(インデックス投資)
損益 -14,120円 (2年後時点+314,410)
高配当株投資
損益 +450,616.2円(2年後時点+902,327.8)
配当金 86,943円
結果としては、2つの投資方法ともプラスになっています。
始めた時期が良かっただけの可能性もあるので、今後も継続して様子を見ていきたいと思います。
ここで皆さんに気をつけて欲しいのは、株式投資は損をしないわけではありません。
私も1年の間にマイナスになっていた時期もありました。
最近は、短期で売買する投資方法にも挑戦していますが、損をしてすごいストレスを感じることもあります。
実際にやってみた感想としては、株式投資はギャンブルではなく、自分に合った方法で準備をすることで資産運用として有効な手段になると思います。
ここからは実際に私が最初に挑戦した2つの投資方法について説明していきます。
積立投資(インデックス投資)
積立投資とは、投資信託などを一定期間ごとに一定金額ずつ購入していく方法です。
購入のタイミングを分散させることにより投資に関するリスクを軽減させる効果があります。
投資信託には様々な商品があり、それぞれに特徴があります。
私は、投資初心者でも始めやすいインデックス指数に連動する投資信託で積立投資をおこないました。
投資信託の場合、運用についてはプロの投資家がおこなうため、忙しくて時間がない人や、購入するタイミングが良くわからないという初心者でも安心して始めることができます。
しかし、投資信託のどれでも良いというわけではありません。
どの投資信託を購入するかしっかり選ぶことが、積立投資で失敗しないために最も重要となります。
・株式投資初心者の人
・長期間での資産形成を考えている人
・株式投資の勉強に時間を費やしたくない人
積立投資(インデックス投資)のメリット
・購入するタイミングで悩む必要がない
株式を売買して差額益を得ようとすると、株価が安い時に購入して高い時に売却する必要があります。
プロの投資家でも株式相場の動きを予測することは難しいと言われており、株式投資を始める初心者の人には難易度が高いです。
また、初心者の人によくあるのが、損をしたくないという気持ちから最初に購入した金額を基準に考え、株価が上昇している優良な銘柄でも、購入した時より高いからと購入できずに利益を得るチャンスを逃してしまうことがあります。しかし、積立投資は銘柄を一度選び、注文日と注文金額を設定したあとは自動的に購入されるため購入のタイミングを考える必要がありません。
よって、積立投資は一時的な相場の動向による欲や期待、不安、焦りなどの様々な人間の心理に影響されることなく淡々と機械的に資金を積み立てる仕組みは、資産形成においてとても有効な方法だといえます。
購入のタイミングを考えないのに利益が出るの?
「ドル・コスト平均法」という考え方によって利益が出やすくなるよ。
ドル・コスト平均法とは、
同じ銘柄を一定額で定期的に購入し続ける方法です。
投資信託を購入するときによく使われます。
1回で購入する場合、ちょうど高値の時に購入してしまう可能性がありますが、定期的に購入し続けることで価格変動リスクを抑えるのに有効と考えられています。
積立期間を長くするほど購入価格は平均化されリスクに強い投資が可能となるので、10年、20年続けるといった長期的な資産形成に効果的です。
株価が安いタイミングで買い続けると損するように思えますが、一定額で買い続けることで、安い時期には多い数量で、高い時期には少ない数量で投資が行われます。
すると長い目で見たときに購入単価を平均化(平準化)することができ、高値つかみを避けることができます。株価が回復、上昇した時には価格が低い時期に多く購入した株により利益がでます。
・手間がかからない
積立投資の目的は長期保有による資産形成なので、頻繁に売却タイミングを考える必要もなく、初心者の方にもやり易い投資方法となっております。
投資信託の場合、ファンドマネージャーというプロの投資家が購入者の人達のお金で日々のニュースや情勢等を考慮して株式の管理を行います。
そのため、自分で情報を収集して値動きを予想し、購入したり、売却したりといった手間を減らせるので、株式投資にかける時間を最低限にできます。
株式投資の勉強がめんどくさい人や、忙しくて時間を取られたくない人でもおこなえる投資方法となります。
その代わり、どの投資信託にするか決めるときには慎重に考えるようにすることが重要と言えます。
・リスクを抑えられる
1つの銘柄に集中して投資をすると、資産運用がうまくいかなくなった時に、その影響はとても大きなものになります。
分散して投資することでそのリスクを比較的抑えることができます。
インデックス指数連動の投資信託を積立投資した場合、
機械的に一定期間ごとに購入するため「時間の分散」、複数の銘柄に投資していることになるので「投資対象銘柄の分散」とリスクを抑えることになります。
より分散投資を意識するには、投資信託の内容を様々な分野の銘柄が含まれているものや、様々な地域、様々な国が含まれているものなどを選ぶことにより、分散効率を上げることができます。
積立投資は、リターンとリスクが安定しやすくなる「長期、積立、分散」が可能な投資方法なため、長期的に運用すれば複利効果で効率良く資産形成を目指すことできるでしょう。
・新NISAのつみたて投資枠で購入できる
株式投資で得た利益には、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%の合計20.315%が課税されます。
利益の約2割が税金として差し引かれるため、実際に手元に残るのは利益の約8割となります。
例えば100万円の利益が出ても、約80万円となります。
しかし、新NISAを利用すると、新NISAのつみたて投資枠で年間投資上限120万円、非課税保有限度1,800万円までで購入した分の運用益は無期限で非課税で受け取ることができます。
・必要な時には現金化できる
定期預金や保険等と違い、必要な時にいつでも売却して現金を受けとることができます。
基本的には長期的に運用を目標とする投資方法になりますが、どうしてもお金が必要となった時には、売却することで現金として受け取ることができます。
iDeCoのように60歳まで引き出せないということがないので、始めるハードルも低くなります。
その他にも
・心理的に安心して保有することができる
株価が下落していても精神的な負担が少ない。
長期投資を目的としているため、長期的に少しずつでも右肩上がりに上がっていけばいいので、日々の株価の上下はあまり気になりません。
・少額からでも投資できる
証券会社によっては、100円から積立投資できるところもあり、まとまったお金がなくても少額から始めることができるため、株式投資初心者の人でも始めやすいです。
無理のない金額から始めて、余裕が出てきたら少しずつ投資額を増やしていくといった自分のペースでおこなうことができます。
積立投資(インデックス投資)のデメリット
・手数料がかかる
積立投資で多く利用される投資信託の場合、手数料がかかります。
➀購入時手数料(販売手数料)
投資信託の購入時に販売会社(証券会社や銀行など)に支払う手数料
②運用管理費用(信託報酬)
投資信託を保有している間、運用・管理にかかる費用として運用資産から差し引かれる手数料
③信託財産留保額
投資信託の売却時に支払う手数料
④その他にも監査法人に支払われるファンドの監査報酬、投資信託が株式を売買する時の売買委託手数料もあります。
手数料は投資信託で異なるため、詳細は目論見書にて確認しましょう。
※最近では購入時手数料、信託財産留保額が無料であったり、運用管理費用(信託報酬)の安い投資信託が増えています。
効率的に資産運用をおこなうためには、運用商品の手数料を比較して選ぶことが大切です。
ちなみに個別銘柄に投資する場合は、②、④の手数料はかかりません。
・個別銘柄など株式投資の知識が増えにくい
投資信託の積立投資をする場合、購入するタイミングは自動で、売却をすることも少ないので売買取引の感覚を養うことが難しいです。また、個別の銘柄について分析することが必須ではないため、企業や業界についての知識は増えにくくなります。
最近では、株式売買のデモトレードができるアプリもあるのでお金をかけずに練習することも可能ではあります。
・短期で大きな利益を出しにくい
積立投資は長期間、資産を一定額ずつ購入することで、価格変動等のリスクを抑える投資方法です。
短期で売買を繰り返して利益を出す投資方法とは違い、短期間で大きな利益を得たいという人にはあまり向かないとも言えます。
10年、20年といった長期目標の達成に向けて、リスクを抑えつつ資産形成を頑張りましょう。
・お金が増えていると感じにくい
利益が出ていたとしても、売却するまではお金が手に入るわけではありません。
もちろん売却すればお金として受け取ることが出来ますが、長期投資が目的なので短期間で売却することはあまりないと思います。
増えている利益を見てもお金が増えている実感が沸きにくいです。
貯金で口座のお金が増えていくのを楽しめる人はいいですが、つまらなく感じる人は積立投資と他の投資方法等で資産形成するのもいいかもしれません。
・出口戦略を考えないといけない
頻繁に売買をするわけではありませんが、将来的には売却してお金に換える必要があります。
自分の資産状況や株価を考慮して売り方や売り時について考えることが必要になります。
積立投資は長期、積立、分散をおこないやすい比較的リスクの低い投資方法です。
また、基本的に自動で簡単に投資できるので初心者の人も始めやすいです。
ポイントはどの商品を選ぶかというところにあります。
投資信託には様々なものがあるので、変な商品を選ばないようにしましょう。
高配当株投資
高配当株投資とは、「配当金」をたくさん出してくれる企業の株式を買って、頻繁に売却するのではなく長期に渡り保有し配当金を受け取る投資方法です。
配当金とは、企業が株主に対して所有する株式数に応じて利益を配分するお金のことです。通常、配当は決算期末に行われます。企業によっては、特別に利益が多かった年や何かしらの記念の時には特別配当や記念配当といった形で通常の配当金に上乗せすることもあります。
高配当銘柄を選定する際には、指標としてよく用いられるのが配当利回りです。
配当利回りは株価に対する1株あたりの年間配当金の割合になります。
計算式は
配当利回り=1株あたりの年間配当金額÷株価×100
(例)
1株1,000円、年間配当金額35円の場合
→配当利回りは3.5%
高配当株とされる水準は明確にはありませんが、個人的には年3.5%以上の配当が見込まれる銘柄は、高配当株と考えております。
高配当株投資も初心者の人でも比較的取り組みやすい投資方法となります。
1株からでも購入することができるため、保守的な人や不安な人は、まず1株から始めてみると下落に対する自分のリスク許容度も理解できます。
・株式投資初心者の人
・不労所得、副収入が欲しい人
・株価の下落にストレスを感じやすい人
・株式投資の勉強をしたい人
高配当株投資のメリット
・定期的に現金で配当金を得られる
日本株は年1〜2回(半年ごと)、米国株は年4回(3か月ごと)配当金を出している企業が多いです。
高配当銘柄を保有し続けることで、定期的に年3〜5%程度の配当金を受け取ることができます。
マイナス金利政策の解除により、銀行預金の利率が0.001%から0.02%程度に上がっている銀行もあるとはいえ、3〜4%という数値は資産運用においてとても魅力的です。
また、キャピタルゲインは売却時の一度だけですが、配当金や株主優待のインカムゲインは無配でない限り、毎年(または毎期)受け取れます。そのため、株価が上昇しない場合でも労働収入以外の不労所得として定期的に安定した収入を得ることができます。
投資家の中には、配当金だけで生活を送る人もいます。ただし、配当金も必ず支払われるわけでなく、その企業が赤字になったり、会社の方針の変更によって減配したり配当金が無くなることもあるので注意は必要です。
・精神的に安心して保有することができる
高い配当金を安定的に多く出している企業は、成熟段階にある大手企業が多く、売上高や利益、業績が安定しているため、株価の変動も緩やかで安定している傾向があります。
株価の変動が激しいと株価が下がって大損するのではないかという恐怖心から、常に株価が気になります。実際に株価が大きく下落するとストレスから仕事が手につかなくなるなど日常生活に影響が出てしまうこともあるでしょう。
高配当株投資の場合、株価が急落しても一定の配当金による現金収入があるという安心感が心の支えになります。また、市場全体が下落している時には、購入チャンスと捉えることもできるため、下落に対するストレスが少なくなります。
配当金は受け取るたびに利益となるので、損益分岐点は下がっていきます。
極端に言うと、配当利回り4%の銘柄を購入し、25年間配当を受け取れば、購入価格分の配当金を得たことになるので、その後に株価が下がっても損をすることがなくなります。ただし、配当金は必ず貰えるわけではないので、現実的に考えると購入金額分の配当金を受け取るのは時間がかかり簡単ではありませんが、長期で配当金を受け取り続ければ実質的に損をしなくなるのは魅力となります。
株価が2、3倍になった時に半分や一部を売却し、投資元本分の利益を確保すれば、その時点で実質的に損はしなくなります。このように、キャピタルゲインとインカムゲインを合計して考えるトータルリターンを安定させることもできます。
・手間が少ない
高配当株投資は、購入したら株式を持ち続けて配当金を受け取ることが前提の投資方法となります。
毎日チャートを見たり、頻繁に売買のタイミングを考えて注文したりする必要がないので、仕事や家庭で忙しい人でも取り組みやすいと言えます。
そのため、購入する時になるべく減配リスクが少なく安定的な配当が期待できる銘柄を選ぶことが重要になります。
基本的に株式を買ってからは長期保有でいいですが、業績の悪化に注意は必要です。
証券会社の企業情報通知機能で決算情報を確認したり、株価通知機能などを利用して株価の暴落を回避するリスク管理をおこないましょう。
・新NISAの成長投資枠で購入できる
株式投資で得た利益には、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%の合計20.315%が課税されます。
利益の約2割が税金として差し引かれるため、実際に手元に残るのは利益の約8割となります。
例えば100万円の利益が出ても、約80万円となります。
しかし、新NISAを利用すると、新NISAの成長投資枠で年間投資上限240万円、非課税保有限度1200万円までで購入した分の配当金や売却益は無期限で非課税で受け取ることができます。
・株の知識が身につく
投資信託と違い、自分で個別の銘柄を選定して保有するので株式投資に対する知識が身につきます。
今後、別の投資方法にも挑戦しようとしている人は、心理的安定がある高配当株投資を行うことで、リスク許容度が低い人でもリスクを抑えつつ実践を通して勉強することができます。
個別の銘柄を自分で見ることになるので、いろいろな銘柄を調べたり、日々の経過をみることで勉強になります。このような出来事があると株価はこう動くのかと保有銘柄ごとに勉強することができます。
いままで興味のなかったニュースやCMに自然と目がいくようになり、政治や経済と世の中の情勢に興味を持つようになるというメリットもあります。
・必要な時には現金化できる
高配当株投資も積立投資と同様に、必要な時にいつでも売却して現金を受けとることができます。基本的には売却することを考えない投資方法になりますが、どうしてもお金が必要となった時には、株を売却することで現金として受け取ることができます。
iDeCoのように60歳まで引き出せなかったり、定期預金や保険等のように途中で現金化すると利益が少なくなってしまうということがないので、始めるハードルも低くなります。
その他にも
・出口戦略を考えなくていい
売却益を狙う投資や積立投資の場合、将来その商品を売ってお金に換える必要があり、売り方や売り時についても(出口戦略を)考えることになるでしょう。
高配当投資は、保有し続けて配当金を受け取ることが目的なので売ることを考えなくてもいい。
高配当株投資のデメリット
・短期間で大幅に資産は増えない
高配当株投資は短期で大儲けできる投資方法ではありません。
成熟段階にある企業が多いため、株価が5倍、10倍になることは少ないです。
短期間で資産を増やしたい人には向かないので、長期間での株価の値上がり、配当金収入による資産形成を目指しましょう。
・減配や無配(配当金の減少)やそれに伴う株価下落などのリスクがある
高配当株の配当金は今後確実に貰えるというものではありません。
企業の業績が悪化したり、経営方針の変更によって配当金が減ったり(減配)、配当金が無くなったり(無配)する可能性もあります。
高配当株は、配当金に魅力を感じて買っている人も多いため、配当金が減れば株価が大幅に下落することもあり、1つ銘柄だけを集中的に購入していると大幅に資産が減少をしてしまうので、様々な銘柄に分散して購入するなどリスク管理が必要となります。
業績の良い企業、配当金を減らさない方針の企業を複数選ぶことが高配当投資の重要なポイントとなります。
・配当金も課税される
株式を売買して得られた利益には合計20.315%の税金が課されます(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)
配当金においても受け取る時に同様に課税されるため、配当利回りの水準より実際受け取れる配当金の金額は少なくなります。
新NISAの成長投資枠を利用することで年間投資上限240万円、非課税保有限度1200万円までで購入した分の配当金は無期限で非課税で受け取ることができます。
高配当株投資は、値動きが激しくないことや配当金を得られるため、比較的リスクを抑えておこなえる投資方法です。
ポイントは、長期的に安定的な配当金収入を得ることです。過去の配当金の実績や業績を確認し、安定的に配当金を出している企業を選びましょう。
もちろん、株価が上昇した際に売却して利益を受け取ることも可能なので、自分に合った資産形成を目指してみるのもいいかもしれません。
まとめ
個人的には高配当株投資の方が気に入っています。
積立投資も資産としては増えていますが、高配当株投資は配当金を受け取るので、副収入として買い物などに使用できるなどお金が増えているという実感が湧きやすいです。
今回紹介した2つの投資方法もあくまで株式投資のため元本保証がありません。投資金額を下回り元本割れになる可能性や配当金が無くなる可能性もあることを念頭に置いておきましょう。
もし元本割れしたくない場合は、定期預金や個人向け国債など元本保証型の金融商品を選ぶようにしましょう。
当ブログ内の株式投資に関する情報は個人の所管であり、投資勧誘や特定の銘柄等の売買を推奨、将来的な価値を保証するものではありません。
株式投資はリスクを伴いますので、銘柄の選択、最終的な売買の判断はご自身で慎重におこなってください。
当ブログでは、投資結果についていかなる損害についても責任は負いかねますので予めご了承ください。
2022年3月楽天証券にて積立投資→2024年1月SBI証券にて積立投資
2022年1月ネオモバにて高配当株投資→2024年1月SBI証券にて高配当株投資
2024年1月SBI証券にて短中期トレード